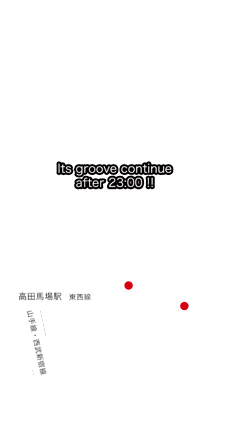トゥルー・ブルーノートの伝説
さァーて原稿を書こうと、「イントロ」のカウンターに腰かけていた俺は、たまたま仕事が休みで店にきていた元アルバイトの吉島に話しかけた。「何かブルーノートのことで、面白い話ないかな」「ブルーノートといえば、亡くなりましたけど、服部良一作曲の<銀座カンカン娘>ですね。ブルーノートの傑作だと思います、これは。よく出来ているし面白いんですよ」
「?・・・・」
アルトサックスを演っている吉島は、学生時代、秩父ジャズ・フェスティバル(というのがあるのだ)に参加、そこで〈枯葉〉を彼のアレンジで演奏。問違えて(?)準優勝しちゃったという経歴の持ち主だ。だからそれなりにジャズには精通している。その吉島が真面目な顔をして、ブルーノートは<カンカン娘>だと言っている。こんにゃろ~俺をおちょくっているのか!俺はむかつきを抑えつつ、「何だそれは?」と聞き返した。
吉島は平然と話を続けた。「マスターご存じないっすか。あの曲はブルーノートを実に効果的に使ってますよ・・・あ、僕の言ってるのは3,5,7度の音を半音下げてブルージィーな響きを生み出す、例の音楽用語のブルーノートのことですけど」
「なんだそうか、そういえばそんなようなバンドマン用語もあったっけな」。俺は話の行き違いにやっと気が付いた。
カウンターのなかで、このやりとりを聞いていた「イントロ」知恵袋の板橋純、すかさずケニー・バレルの『ミッドナイト・ブルー』(4123)をレコード棚から取り出した。この盤はブルース・ジャズ・ギターの金太郎飴アルバムで、全編に渋いブルースがむせび泣いている。はまり込んで聴いていると、この明るい俺までつい落ち込んでくるからスゴイ説得力だ。何の悩みもない気楽な人生を送っている方は、一度聴いて暗くなってみてください。さて板橋締は1曲目のブルース、<チトリンス・コン・力ーネ>をかけながら、「ほらここ、このフレーズ!」てな具合に、吉島といっしょになって実地解説してくれた。そうかブルーノートといっても、レコード以外にもいろいろあるんだなァと感動して、思わず吉島にビールをおごってしまった。
それにしてもブルーノートとは、レーベル名にせよ音楽用語にせよ艮いネーミングだ。これがソウルノートならまあまあだけど、ピンクノートや、宿題ノートだったら興ざめしちゃうもんね……。
さて周知のように、ブルーノートとジャズ喫茶は昔から深いつきあいだ。店を盛り上げる起爆剤としてのブルーノート盤は、ジャズ喫茶に無くてはならないし、ジャズ喫茶で聴いたその盤を探し求めてレコード屋に足しげく通ったのは俺だけではない筈だ。少なくともこの文章を読んでいるような特殊な(?)人には、身に覚えがあるだろう。多くの人にとってジャズ喫茶が青春で、ブルーノートが恋人だった。この両者の友好関係は日米貿易摩擦とは無関係に、今でも揺るぎないものがある。
そのブルーノートの膨大なカタログのなかでも、今手にしているこの盤は、俺にとって特に忘れることができない。
ジャケット中程に幻のテナー奏者ティナ一ブルックスの小さな写真、その下にはトゥルー.ブルーとある。”俺がトゥルー・ブルーノートだ”といっている風情だ。コーティングされてツルツルの、ぶ厚いジャケットの周りは、タバコのヤニで黄色っぽくなっている。裏ジャケットにはBN4041とあるが、その脇に277と謎の番号がゴム印で押してある…-。実はこれはあるジャズ喫茶の整理番号だったのだ。今から27年前に店を閉めた中野「クレッセント」のコレクションで、おそらくオーナー松田さんが277枚目に購入したのだろう。中の盤を取り出すと、百何十回は掛かったと思われる名誉のスリ傷で盤が真っ白だ。重針圧用のオルトフォンでそれだけ掛ければ白くもなろう。だがブルーノートのオリジナル盤はタフなのだ。今こうして聴いていても、骨太で独特のブルーノート.サウンドがオリジナルに甦る。そしてそれを聴いているといつも俺は、ふっと昔の或る情景にタイムスリツプしてしまう….
今から30年程前、十代の終わりにその「クレツセント」でアルバイトをしていた頃のことだ。
コーヒーをたてる合間を縫ってレコード室に入り杁み、時間さえあれば知らない盤に見入っていた。レコードに溺れる毎日だった。当時気に入っていたのは、フレディ・ハバードのハードバップ盤だ。「クレツセント」のレコード室で、初期のブルーノート・リーダー作3種を発見したからだ。それまでは音楽的にソフイステイケイトされて少々コマーシャルなアトランティック盤や、ブルーノートの後期盤しか知らなかった。その俺の耳にデビューしたてで怖いもの知らずのハバードの炸裂音は、荒削りだが実に新鮮だった。それらは初リーダー盤『オープン・セサミ』(4040)『ゴーイン・アップ』(4056)『ハブ・キャップ』(4073)の三枚だ。『ゴーイン・アップ』はは当時それなりにセールスを記録したせいか、そこそこジャズ繋で見かけたが、後の二枚、特に『オープン.セサミ』は、多くの有名ジャズ喫茶にもあまり無かった。ある日松田マスターに、『オープン・セサミ』をレコード棚の隅から発見したこと、聴いてブッ飛んだこと、他の店では見たことが無いことを話した。彼はニコニコしながら脚立の上に乗って、普段全くと言ってよい程掛からないレコード棚から、前述のティナ・ブルックスの『トゥルー・ブルー』を出してきた。よく見るとセサミとレコード番号が続きではないか。パーソネルもピアノとドラムス以外はいっしょ。録音日もその6日後で、いわばハバード初リーダー吹込みの姉妹盤。早速聴いてみた。これまた素晴らしい。ピアノがマッコイからデュiク・ジョーダンに替わって、ゼサミとはちょっぴり違った味を出している。ジャケットの挨が拭き取られると、その日からは「クレッセント」御自慢の幻の名盤コーナーに置かれることになった。もちろん時々掛けられるようにだ。今は再発盤が出ちゃったから、あまり有難味が伝わらないだろうけど、その頃は「クレッセント」でしか聴けない超幻盤であった。
聴くだけでは飽き足らぬ、俺もこういう名盤が欲しい….。しばらくしてアルパイトを辞めてからは、逆にますますジャズの深みにはまっていった。なんとその後、水道橋のジャズ・レコード専門店、「トニイ・レコード」で俺は3年問働くことになるのだ。年問何万枚もの中古直輸入盤が入荷する「トニイ」で働きだしてからは、そんじょそこいらの幻の名盤なんぞでは、ビクともしなくなった。その当時のブルーノート超入手困難盤というと、『J・R・モンテローズ』(1536)や、ルイ・スミスの二枚『スミスビルL(1594)、『ヒァ・カムズ・ルイ・スミス』(1584)などといわれていた。それでも「トニイ」には何度か入荷したし、オークション・リストで金に糸目さえ付けなければ、大体の盤は手に入れることが出来た。だが『トゥルー・ブルーLだけは入らなかった。リストで見たことすら一遍もない。そして月日は流れ、時は膝腱と飛び続けた。
俺は「イントロ」開店準備のため、お世話になった「トニイ・レコード」を辞めたが、よく遊びには行っていた。レコード屋巡りと飲酒の習性というのは、なかなかやめられるものではないのだ。その帰り道、中野に住んでいた俺は毎日のように「クレッセント」に寄って、マスターとレコード談義にひと花咲かせる・・・・・。そんな或る日、「クレッセント」でビールを飲んでいると、マスターがいつもと違う真剣な表情で近付いてきて言った。「ジャズ喫茶を閉めるから、レコードの処分を手伝ってくれ」。もちろん冗談だと思うから笑って聞いていたら、「本気なんだ。ジャズはもうたっぷり聴いた。また別のことを始めたいんだ。ジャズだけに人生の全てを売り渡す訳にはいかないからね」。周りを見渡してもお客さんはそこそこ入っている。営業的に閉鎖に追い込まれるような状況には、傍から見る限りない。今俺が同業者になって、その時のことを思い出してマスターの気持ちを推しはかってみても、いまだに俺は分からない。ただ分かるのは、この世には人の数だけの人生があるってことだけだ。マスターのハラはもう決まっているようだった。俺は、彼もよく知っている「トニイ・レコード」を紹介した。
かくして「クレッセント」の一大コレクションは放出された。その時、形見分けのように譲り分けてもらったのが、この『トゥルー・ブルー』だ。あれ程欲しかった盤が、「クレツセント」のバイト時代の思い出と共に、いきなり手に入ってしまった。そしていまだに俺の手の中にあって、青春の思い出を温め直しながら、「イントロ」で息づいている。
2000年1月 『ブルーノート再入門』(出版:朝日文庫)のために執筆